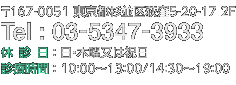マウスガード(スポーツ歯科)
マウスガード(スポーツ歯科)
1)スポーツをされている方へ
“マウスガードの装着によって力が出る”という話はよく耳にするところです。
ナショナルトレーニングセンター(通称トレセン)のデータによると、
筋力のアップは認められ、パフォーマンスはアップするというデータがあるのは事実です。
しかしながら、一般の人が想像するような著しいほどの顕著な筋力アップまでは認められなかった、 ともされています。
一方で最も顕著な結果として、マウスガードを適切に装着することで「体軸が安定する(体幹が良くなる)」 ということが証明されました。
またデータでは、スポーツのケガは試合中の本番ではなく、練習中に最も多く起こることが示されています。
マウスガードを着けていない人と着けている人では、着けていない人のほうが外傷発生リスクは1.6~1.9倍高く、 スポーツの競技数と人口の増加、スポーツ競技の多様化、高度化と相まってケガの事故は近年増加傾向にあり、 1年間に9万人ものスポーツ選手がいわゆるケガをしているとされています。(財団法人スポーツ安全協会調査 平成8年)
競技種目としては、ラグビー(21.6%)、スキー(20.3%)、野球(13.5%)、サッカー(10.8%)の順に多く、
事故の原因としては対人との衝突が60.8%と最も多い。
野球やサッカー、バスケット、ホッケーなどの道具を使うスポーツはもちろん、普段の体育活動においてもマウスガードの装着が推奨されています。
外傷として“歯が折れる”のは統計的に小学校、中学校、高校、高等専門学校が多く、
運動能力(技術スキル・筋肉パワー・呼吸循環機能)の高まりとともに
発生件数は増加し、特に10代~20代の男性の受傷で多く、上の前歯が圧倒的に多いのです。
かならずしもスポーツのみとは限りませんが、それでもスポーツ時には転んだり、接触したり、ボールや用具がぶつかったりすることが多いので、歯が折れるなどの口の中のケガ防止、また先に記した通り本番中よりも練習中に起きるケガが多いことからも、やはり練習中から常時マウスガードを装着しておくことが望ましいのです。
2)マウスガードの仕上がりがアスリートの成果を左右する!?
「もっと早くちゃんと作っておけば良かった・・・」
プロボクサー選手が引退試合の直前に、実際に言った言葉です。
「市販の(マウスピース)だと、試合中に苦しくて上手く呼吸できなかった。」
「こんな風にマウスピースがしっかりしていると、呼吸が楽にできる。」
「早くからこれを使っていれば、もっと勝てたかも知れない・・」
とも言っておりました。
プロボクサー選手に限らず、ラクロスのナショナルチームの選手の方など、その分野の第一線で活躍されている方も、当院にてマウスガードを作られました。
スポーツ時に緊張したり、体の疲れに従い、合わないマウスガード(異物)があると、
それをストレス(異物)に感じてしまうようです。
そういった点から、なるべく“違和感の少ない”こともマウスガード作りを進める上で
気を付けています。
スポーツによっても基本設計は、多少異なります。
例えばボクシングなどの打撃系のスポーツは、打撃の衝撃力を分散・吸収させる必要があるため、適切な厚みをとった弾性に富んだ保護面を確保するのは勿論、あえて丸みを帯びて作成する必要があります。
直接外力を受ける打撃系は、外側をツルンとさせることで応力を逃がすことができるようになり、優れた外傷防護能でダメージを減らすことができます。
そのためにも歯肉を覆う必要はありますが、過剰に歯肉を覆ってしまうと、今度は違和感が増してしまいます。
そこで当院では違和感を最小化できるようにマウスガードの周りのフチ部分(端)を薄く設計するなど、様々な工夫も凝らしています。
一方で防具を装着しておこなうスポーツの場合は、やや薄めに作ったり、極力マウスガードを装着している存在感(違和感)を少なくするために、歯の形に添うような作りをする場合もあります。(スポーツによっては少しずつ厚みを変えたり、個人の好みによっても変化させたりしています)
また、競技の種類によって“マウスガードが外れないことで安定感を得ること”を第一の目的とする必要がある場合には、裏側の歯肉を一部覆うこともあります。
- スポーツ中に大声を出すことや、疲れて苦しくなり、口で息をするようになってくることが想定されるような場合には、特に口を開けても落ちないように考えて作製します。
- 違和感が強く苦しい方(嘔吐反射のようにオエッとなる人)の場合には、逆に裏側の歯肉にマウスガードのフチ(端)が当たらないように工夫して作製したりもします。
- ときにはマウスガードを噛んだままでも呼吸ができるように、空気の通る溝をあえて確保して作る場合もあります。
- また、体軸・体幹のバランスをより重視し、力が発揮できるように奥歯の噛む部分を意図的に平らでフラットな面で作製することもあります。
マウスガード装着を推奨するスポーツとしては・・
アクロバット、武術、総合格闘技、空手、ラグビー、ラケットボール、野球、自転車競技、バスケットボール、砲丸投げ、スキー、スケートボード、ボクシング、キックボクシング、フィールドホッケー、インラインホッケー、乗馬、サッカー、スカッシュ、ソフトボール、アメリカンフットボール、ハンドボール、体操、サーフィン、水球、バレーボール、アイスホッケー、ラクロス、インラインスケート、ウエイトリフティング、スカイダイビング、レスリング、バンディ、モータースポーツ
※砲丸投げやウエイトリフティングなどの接触のないマウスガード推奨の理由は、力を込める瞬間に無意識に歯を食いしばっている場合が多く、それに伴う自傷や障害、事故の防止を目的としています。
完全義務化では・・
アメリカンフットボール、キックボクシング、ボクシング、テコンドー、総合格闘技、女子ラクロス、
ラグビー(高校生以下・医歯薬大学リーグ・西日本医学体育大会)、
※特にラグビーは高校生に限らず、中学生以下のジュニアラグビーにもマウスガード着用が義務化されるようになりました。
一部義務化には・・
空手、アイスホッケー、インラインホッケー
逆に、試合中でマウスガードの使用禁止なのは・・
柔道
種目によってマウスガードに使用できる色、仕様が“制限されている”場合もあり、
| ボクシング | :赤は不可 |
| アイスホッケー | :透明、白、肌色は不可 |
| アメリカンフットボール | :透明、白は不可(明るい色で) |
| キックボクシング | :ストラップ付は不可 |
| バスケットボール | :透明に限り可能 |
| 硬式野球 | :透明または白に限り可能 |
| モータースポーツ | :口の中の出血が確認しやすい色で |
となっています。
3)マウスガードと一言でいっても!?
市販品は安価ですが上手くフィットせずに合わないことが多く、スポーツ時に良いパフォーマンスが出ないこともあり得ます。
市販製品を皆さんが使わなくなってしまうのは、市販品は個人の歯並びやかみ合わせを考慮していないがために、しっかり合わずに隙間が生じ、落ちやすいことが一番の理由です。
「カパカパして邪魔くさい」との声も聞きました。
効果の面でも衝撃の吸収が弱いため、あまり本来の効果が期待できない点や、俊敏的動きや瞬発的な動きなど、全ての歯の接触によって得られる“力の発揮や体軸・体幹の安定”などは、市販品ではなかなか作りえないのも課題といえるでしょう。
市販品と歯科作成のオーダーメイド品との大きな違いは・・
| ・ | オーダーメイド品は市販品に比べてぴったりに作成しているので装着感が違う |
| ↓ | |
| ・ | 結果的に口を開けても落ちにくく、呼吸も比較的楽である |
| ↓ | |
| ・ | それゆえに試合中の戦術、フォーメーション指示、ポジション確認などの声掛けなどでも口を開けて会話ができる |
| ↓ | |
| ・ | また個人ごとにかみ合わせのバランスを考慮して作っているので、体軸の安定やパフォーマンス向上などの 期待ができる |
世界最古のマウスガードは1892年(明治25年)にイギリスロンドンの歯科医であったWoolf Krause氏がプロボクシング選手の依頼を受けて作成したものと言われています。
また、アメリカ最古のマウスガードは1916年(大正5年)にシカゴの歯科医師Thomas A. Carlos氏の制作したボクサー用のものでした。
一方で日本初のマウスガードに関する論文を発表したのは1925年(大正14年)歯科医師の大久保信一氏で、やはりボクサー用のものでした。
このように、歴史的知見からもマウスガードの制作は“歯科医師が担い、進化させてきた”のです。
4)似て非なるもの
スポーツに使うマウスガードと、歯ぎしりや食いしばり・顎関節症の治療に用いるマウスピース(スプリント)は異なります。
- 基本的にはスポーツに使うマウスガードは比較的やわらかいソフト系、
- 顎関節症などの治療に用いるスプリントは硬めのハード系の素材で作ります。
(まれにスポーツ用マウスガードでもハード素材を使用することもあります)
スポーツ用のマウスガードは
- 外傷などのケガからの保護
- 瞬発的な過加重な噛みこみによる歯の破折、詰め物などの破損の防止や保護
- 体軸・体幹のバランスが良くなることで結果としてパフォーマンスの向上につなげること
などが主な目的です。

スポーツ用マウスガード 例1 |
スポーツ用マウスガード 例2 |
スポーツ用マウスガード 例3 |
マウスガード作成料(税別):18,000円~(単色)
一方で治療に用いるスプリントは
- 顎関節症では顎関節の負担軽減による関節自体の安静や安定
- 歯ぎしりや食いしばりでは歯の摩耗や揺れの保護や防止
- 睡眠時無呼吸症候群治療を目的として作成するスリープスプリントは気道確保(無呼吸の緩和)
が目的となります。

治療用スプリント |
スリープスプリント |
上記に挙げたように、スポーツの種類や疾患などによって、マウスガードやマウスピースの使用目的は全く異なります。
ゆえに、それぞれに合った材料と作り方が必要になってきます。
デンタルオフィス宮村では個人の意向を聴き、極力装着時にも邪魔にならず、噛みこんだ時でも呼吸が楽にできるよう、そして、選手個々のパフォーマンスが少しでも向上する手助けができるよう努めております。
【著者】デンタルオフィス宮村
院長(歯科医師) 宮村壽一